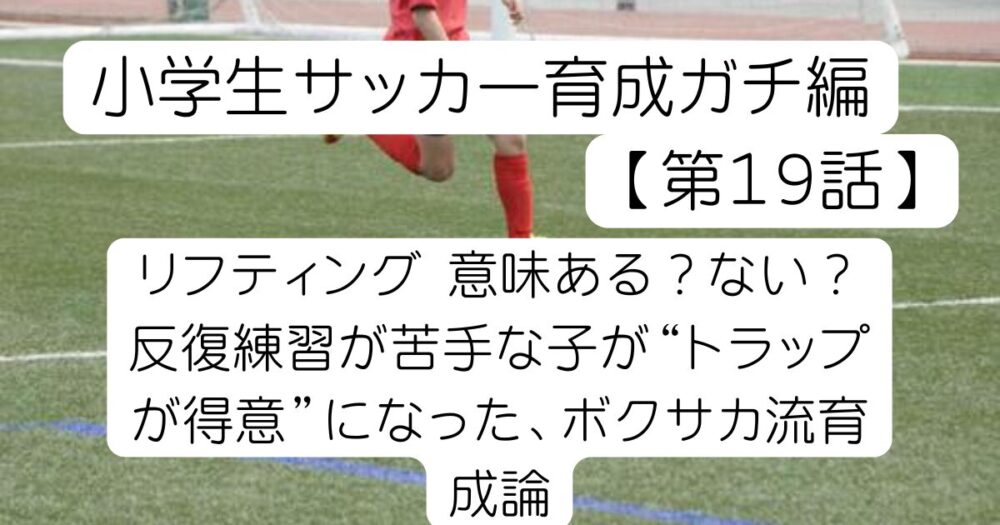小学生サッカー育成ガチ編【第19話】:リフティング 意味ある?反復練習が苦手な子が“トラップが得意”になった、ボクサカ流育成論
こんにちは!
「リフティングって、サッカーの試合で本当に意味があるのかな…?」
「リフティングができないと、やっぱりサッカーは上手くなれないんだろうか…?」
地味な反復練習がなかなか続かないお子さんの姿を見ながら、
そんな風に、期待と不安の狭間で、心が揺れ動いている親御さんも少なくないのではないでしょうか。
心のどこかで
「リフティングができなくても大丈夫だよ」と肯定してあげたい気持ちと、
「でも、やっぱりできるようになってほしい」と願う気持ち。
その葛藤、痛いほどよく分かります。
我が家の長男も、まさにそうでした。リフティングなんて、”50回すらできたことがなかった”んです(苦笑)。
地味な反復練習が大の苦手で、すぐに飽きてしまう。
そんな彼が、ある時を境に、チームメイトから「あいつはトラップが上手い!」と、尊敬の眼差しで見られるようになったんです。
その秘密は、終わりのないリフティングの反復練習ではありませんでした。
リフティングという「手段」と、サッカーが上手くなるという「目的」を一度切り離し、
親子で楽しみながら取り組んだ、全く別の角度からのアプローチにあったのです。
この記事では、リフティングが苦手だった長男が、いかにしてトラップを得意な武器に変えていったのか。
その具体的な練習方法と、親子で共有した「意識」について、お話しさせていただきたいと思います。
それではどうぞ!

そもそも「リフティング」のゴールは何だろう?~意味がある練習、ない練習~
まず、大前提として、皆さんと一緒に考えてみたいことがあります。
それは、「リフティングを上手くさせたいゴール(目的)は、一体何でしょうか?」ということです。

「100回、1000回できること」がゴールになってしまうと、それはもはやサッカーの練習ではなく、リフティングという別の競技になってしまいます。そして、多くの子は、その果てしない回数を目指す過程で、楽しさを見失ってしまう。
でも、もしゴールが「試合で使える、正確なボールコントロールを身につけること」なのであれば、話は変わってきます。
例えば、「トラップ」を上手くするための練習なら、リフティングから入るのも良いかもしれませんが、
- 親子での対面パス
(相手の矢印を折るトラップ練習はこちら)
(対面パスで遊んだ記事はこちら) - 壁パス
(壁パスの記事はこちら)
のように、試合を想定した練習の方が、より実践的で、子供も楽しみながらトラップが上達できる手段があると、私は考えています。

そして、その対面パス練習を、さらに細分化し、「ボールの中心を、体の色々な部位で正確に捉える」という、ミクロな視点での練習が必要になった時、そこで初めて、いわゆる「リフティング練習」が、本当の意味を持って輝き始めるのではないでしょうか。
つまり、リフティングは目的ではなく、あくまでボールコントロールという大きな山を登るための、数ある道具の一つに過ぎないのです。
我が家の「無理にリフティング練習させない」トラップ練習法~長男との試行錯誤から生まれた4つの秘訣~

ここからは、リフティング練習が苦手な長男と、それならこうすればいいんじゃねと閃いた私が、試行錯誤の末に見つけ出した、とっておきの「トラップが上手くなる」ための、4つの秘訣をご紹介します。
秘訣①:できなくても良いじゃない♪視点を変えてアイディアを考える。

まず私がやったのは、リフティング練習の様な地味な自主練ができない長男を「肯定してあげる」ことでした(笑)。そして、前述したように、代わりに二人で「試合に活きる対面パス練習をする」。
この作戦が、すべての始まりでした。
秘訣②:練習を「試合の場面」に落とし込む!

そこで、ただの対面パスではなく、試合であり得るシチュエーションを練習に持ち込みました。
長男は当時、サイドハーフでプレーすることが多かったですが、FWや中盤、トップ下など様々なポジションも試されていたため、
- 「サイドで、DFを背負いながらパスを受ける場面、並走しながら受ける場面」
- 「中盤で前を向きたいのに、相手が詰めてくる場面」
- 「裏抜けした際に、後ろからの浮き球を前に治める場面」
などなど..
子供が実際に「苦手だな」「困るな」と感じている場面を”再現”し、
その中でのパス交換を繰り返したんです。
我が家の親子練習の方針は「課題に特化して、楽しく技術を磨くこと」。
当然、保護者は指導者ではありません。だからこそ、チーム練習では手が回りにくい部分を拾い、家庭で細かな技術練習メニューを考案。親子で競い合いながら、一緒に上達していく方法を選びました。
仮に経験者じゃない保護者さんでも「お子さんの苦手な場面を作って一緒になって練習する」
別に親が見本の様に完璧に出来なくてもいいんです。それがまた、親子のコミュニケーションになるんですから。
秘訣③:「止める」の呪いを解く!最適な場所に「置く」という意識改革

「止めろ!」「ちゃんとトラップしろ!」
と言いがちですが、この「止める」という言葉の呪いを、私たちは解くことにしました。
そうではなく、
「自分が次にやりたいプレー(ドリブル、パス、シュート)に、一番最適な場所にボールを『置く』んだよ」と。
- スペースが空いているなら、そのスペースに。
- 相手の逆を取りたいなら、その逆側のスペースに。
- 足元で勝負したいなら、ピタッと吸い付くように足元に。
この「止める」から「置く」への意識改革が、彼のトラップに「目的」と「意図」を与えてくれました。
秘訣④:魔法の感覚!「面」ではなく「点」で捉えるボールタッチ術

そして、意図した場所にボールを「置く」ための、技術的な核心がこれでした。
それは、ボールを”足”の「面」でベタッと止めようとするのではなく、
『点』を意識して、ボールの勢いに合わせて弾くように触れる、というものです。
- インサイド = 親指の付け根の出っ張った骨の下辺り
- アウトサイド = 小指の付け根の出っ張った骨、あるいは下辺り(面で触れた方が良いケースもある)
など、細かい部分にこだわって練習します。
人によって、あるいはその時のプレーによって、やりやすい『点』は変わるので、
そこも子供と一緒に「パパはここがやりやすいかも♪」「ボクはここだな♪」なんて言い合いながら練習すると面白いと思います。

さらに、その感覚を研ぎ澄ますために、親子でこんな実験をしました。
「ボールの中心に、もっと小さい玉みたいなボールが入っているとイメージしてみよう。その中心の『核』を、足の『点』で触ってみよう」と。
この、細部にまでわたって徹底的に意識する、ちょっぴりマニアックな遊びが、彼のボールタッチを劇的に変えたんです。
これらの練習を、決して厳しいトレーニングとしてではなく、あくまで「遊びの延長」として、親子で楽しみながら続けていきました。


中学生になった長男と、リフティングとの“再会”そして“開花”

そんなこんなで、リフティングは苦手なまま6年生になった長男ですが、
目的意識のあるトラップ技術のおかげで、チームの中でも効果的なプレーができる選手へと成長していました。
(※チャレンジしているので、もちろんミスはありますよ?)
そして、中学生になり、ジュニアユースの強豪チームに入団。
そこでは、なんとウォーミングアップで、リフティングが必須メニューとして組み込まれていたのです!
インサイド、アウトサイド、もも、頭…各部位ごとに、コートの端から端までリフティングをしながら移動する練習。もちろん、入団当初の長男は、チームで一番下手でした(苦笑)。
しかし、3年間、仲間と共にリフティング練習を続ける中で、彼は少しずつ、しかし着実に上達していきました。そして、驚くべき化学反応が起こったのです。

ジュニア期に、実戦的な親子パス交換で培った「トラップの目的意識(どこに置くか)」と、
ジュニアユースのリフティング練習で習得した「ボールの中心を捉える細かい技術意識」が、
彼の頭と体の中で、見事に融合したのです!
その結果、彼は、チームで1、2を争うほどの「トラップ名人」へと変貌を遂げました。
(※あくまでチーム内での話ですが…一応、強豪チームです(笑))

まとめ:リフティングができない君へ、そして悩める親御さんへ
この長男の経験から、私が皆さんに一番伝えたいこと。
それは、ジュニア期にリフティングができないからといって、決して悩んだり、ましてや練習を強要したりする必要はないということです。
そして、お子さんがリフティングが苦手だからといって、その子がダメな選手だなんてことは、絶対に、絶対にありません。
もちろん、リフティングが上手いに越したことはありません。それは、素晴らしいボールコントロール技術の証です。でも、長男の成長を間近で見て、サッカー選手として成長する道は、決して一本道ではないんだと感じました。
リフティングのような地味な反復練習が苦手なら、親子での対面パスのように、もっと実戦的で、楽しい練習から「トラップのコツ」を掴んだっていい。
そして、体が成長し、サッカーへの理解が深まった中学生くらいから、改めてリフティングという「細かい技術」と向き合ったって、決して遅くはないと思っています。
大切なのは、回数や見た目の派手さではなく、
その練習が、どんな「目的」に繋がっているのか。そして何より、お子さん自身が「楽しい!」と感じながら、ボールに触れているかどうか。
私たち親の役割は、子供を一つの型にはめることではなく、その子の個性や興味に合わせて、たくさんの「楽しい入り口」を用意してあげることなのかもしれませんね。