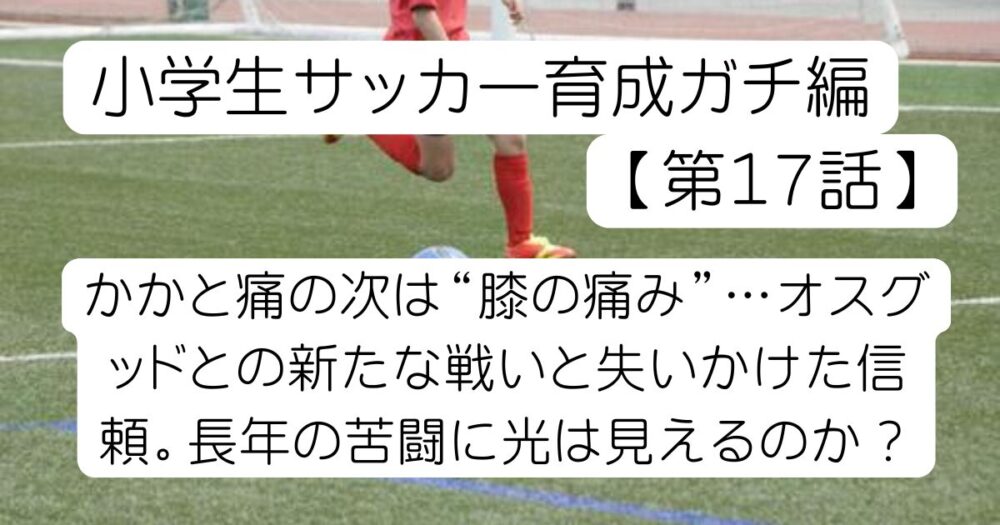小学生サッカー育成ガチ編【第17話】:かかと痛の次は“膝の痛み”…オスグッドとの新たな戦いと失いかけた信頼。長年の苦闘に光は見えるのか?
こんにちは!
「一つの山を越えたと思ったら、また次の、もっと険しい山が目の前に現れる…」
子育てとは、そして子供の成長を見守るとは、まさにそんな連続なのかもしれませんね。
前回の記事で、長男が小学生時代、長く続いた「かかとの痛み」と戦ってきたお話をさせていただきました。そして、その長いトンネルの先に、ようやく希望の光が見え始めたかのように思えた、矢先のことでした。
(前回の記事はこちら)
中学生になった長男がある日、ポツリとこう言ったんです。
「パパ、今度は…膝が痛い…」
その言葉を聞いた時の、私の正直な気持ちを白状しますと、「またか…」という、深い、深いため息でした。
かかとの痛みがようやく落ち着いてきたというのに、今度は膝。
親として、彼の体のことを心配する気持ちはもちろんですが、同時に、また始まるであろう、終わりの見えない痛みとの戦いに、心が少しだけ重くなったのを覚えています。
今日は、そんな長男を新たに襲った「膝の痛み」、いわゆる「オスグッド病」との出会い、そしてそれが彼のサッカー人生、さらには親子関係にまで落とした影について、包み隠さずお話ししたいと思います。
それではどうぞ!
安堵も束の間…長男を襲った新たな痛み「オスグッド病」との出会い
シーバー病による「かかとの痛み」が、成長と共になんとか落ち着きを見せ始めた頃。
安堵したのも束の間。
長男の新たな敵は、「膝」に現れました。
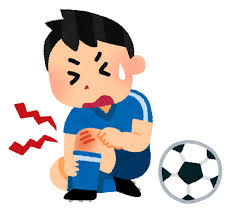
特に、ボールを蹴る動作や、ジャンプからの着地、そして不意の接触プレーで、膝に鋭い痛みが走るというのです。
私たちは、またあの整形外科の門を叩きました。
そして告げられた診断名は、「オスグッド・シュラッター病」。
先生の説明によると、
「膝のお皿の下にある、出っ張った骨(脛骨粗面)が、太ももの前の大きな筋肉(大腿四頭筋)に強く引っ張られることで炎症を起こしてしまう、これもまた成長期に特有の痛みなんですよ」
とのこと。

まさに、シーバー病の「膝バージョン」のようなものでした。
特に、長男が一番辛そうだったのは、
相手との接触で膝同士が「ゴツン!」と当たった時の、あの激痛です。
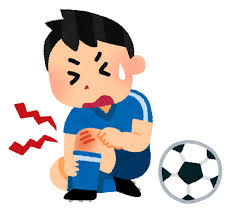
一度それを経験すると、どうしてもプレーが消極的になってしまう。相手との競り合いを避け、ボールを受けるのを怖がるようになっていきました。
「ケガも実力のうち」監督の言葉と、失いかけた信頼という“心の痛み”
肉体的な痛みもさることながら、当時の長男を、さらに苦しめたのが、
監督からの信頼を失ってしまうかもしれないという、目に見えない「心の痛み」でした。
長男がお世話になっていたチームの監督は、熱心で素晴らしい指導者でしたが、同時に、怪我に対する考え方が非常に厳しい方でした。
「日々の体のケア、準備。それらを怠るから怪我をする。つまり、ケガも実力のうち」

という哲学をお持ちだったんです。
もちろん、その考え方はごもっとも。自己管理能力も、サッカー選手としての大切なスキルの一つですからね。
特に、強豪のクラブチームほど、こうした意識が徹底されている印象があります。
しかし、成長期特有の、いわば「避けるのが難しい痛み」を抱える長男にとっては、その言葉が重くのしかかりました。
そんな焦りと不安から、長男が痛みを我慢してプレーしようとしていた姿を見るのは、親として本当に、本当に辛いものでした。そして、そんな彼に「無理するな、休め」と言えない親自身の無力さに、歯がゆい思いを募らせていました。
なぜ痛む?犯人は膝だけじゃなかった!「太もも」と「ふくらはぎ」の硬い筋肉
かかとの痛みの時と同じように、私たちは「なぜ、長男の膝はこんなに痛むんだろう?」という、原因の探求を始めました。そして、やはり今回も、痛みの“本当の犯人”は、膝だけにいるわけではないことが分かってきたんです。
- 犯人候補①:「太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)」の硬さ
オスグッド病の直接的な原因とも言えるのが、この筋肉の硬さです。サッカーのキックやダッシュで日常的に酷使されるこの大きな筋肉が、ストレッチ不足などでガチガチに硬くなると、膝のお皿を通じて、痛みの震源地である膝下の骨を、常にゴムのようにギリギリと引っ張り続けてしまうんです。成長期の柔らかい骨は、その強い張力に耐えきれず、炎症を起こしてしまうんですね。 - 犯人候補②:見落としがちな「ふくらはぎの筋肉」の硬さ
そして、意外と見落としがちなのが、ふくらはぎの筋肉の硬さです。実は、ふくらはぎの筋肉が硬いと、足首の動きが悪くなり、走ったりジャンプしたりする際の衝撃吸収がうまくできなくなります。その結果、体全体のバランスが崩れ、膝に余計なねじれや負担がかかってしまう。これも、痛みを悪化させる大きな要因の一つでした。
痛みが出ているのは「膝」でも、その根本的な原因は「太もも」や「ふくらはぎ」といった、別の場所にある。
この、体の連動性についての理解が、後の劇的な改善へと繋がる、重要な伏線になっていたのです。
試行錯誤の日々…テーピングとストレッチ、そして「継続の壁」との再戦
原因が少しずつ見えてきたことで、私たちは再び、改善への道を模索し始めました。
藁にもすがる思いで、インターネットや本で調べては、テーピングを試しました。
膝のお皿の下の、出っ張っている骨に巻いてみたり、太ももの筋肉の動きをサポートするように巻いてみたり。
確かに、テーピングをすると、少しは痛みが和らぐようでした。
しかし、それはあくまで一時的な対処療法。根本的な解決には至りません。
そして、原因である筋肉の硬さをほぐすためのストレッチ。
「よし、今日から毎日、お風呂上がりに太ももとふくらはぎのストレッチだ!」

親子でそう誓い、最初の数日は頑張りました。
しかし…かかとの痛みの時と、全く同じ壁に私たちは再びぶつかりました。
そう、「継続の壁」です。
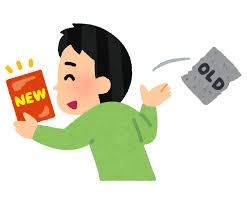
地味で、即効性があるわけではないストレッチを、サッカーで疲れた後に、子供が毎日続けることの難しさ。
そして、なかなか改善しない状況に、「本当に意味があるのかな…」と、モチベーションが下がっていく。
そして気付けば、また「”一人”ストレッチ(笑)」

あの時と同じように、私たちの試行錯誤は、またしても暗礁に乗り上げてしまったのです。
まとめ:終わらない痛み、しかし諦めない先に…次こそ、光は見えるのか?
結局、この膝の痛みも、小学生の間、そして中学生になってからも、しばらくの間、長男を苦しめ続けることになります。
かかとの痛みから始まった、長く暗いトンネル。出口は見えず、今度は膝の痛みという、新たな闇が私たちの前に広がっていました。
でも、今だからこそ言えることがあります。
この長く暗いトンネルのような日々が、実は、私たち親子を“本当の解決策”へと導いてくれる、最後の、そして最も重要な試練だったんです。
その奇跡のような「解決編」のお話は、いよいよ次回の記事で、詳しくお話しさせていただきたいと思います。