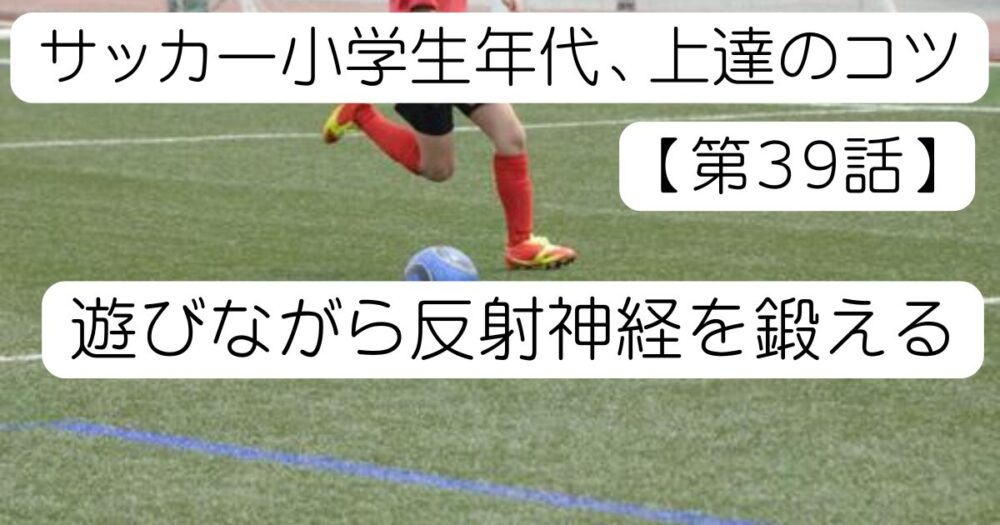サッカー小学生年代、上達のコツ【第39話】:遊びながら反射神経を鍛える
こんにちは!
前回は「スペースを見つける」ため、リフティングをしながら足し算をして「首振り」の技術を身に付けるという記事をご紹介しました。低学年の内に「首振り」が出来れば、よりプレーの幅も広がるので、ぜひ親子でやってみて下さいね♪
さて本記事では、親子で「反射神経を鍛える練習」をしたお話をご紹介します。
それではどうぞ!

色違いのマーカーを使って対決
青と赤のマーカーコーンを使います。
プレーヤーが2人真ん中に立ち、両端にそれぞれ青と赤のマーカーコーンを置きましょう。プレーヤーからマーカーコーンまでの長さの設定は反射神経トレーニングなのでせいぜい”2メートルくらいの間隔”で良いと思います。
我が家の場合は、長男と次男を中心に両端に青と赤のマーカーコーンを置きます。
準備が出来たら勝負開始です!

語尾の「お」と「か」で判断。ダッシュしてタッチする!

例として”指示役”が、「赤!」と指示したら、”プレーヤー”は赤色のマーカーコーンにダッシュしてタッチします。先にタッチしたプレーヤーが勝ち。
青と赤のマーカーコーンで行う場合、最初の「あ」までは一緒なので、プレーヤーは語尾の「お」か「か」で判断することになります
アレンジ版!ボールと帽子で代用


「あ、マーカー忘れた!」って時でも身の回りの物で代用出来ます。
我が家の場合、「帽子」と「ボール」を使って同じ練習をしてました。
「ぼーーー…ーし!」
「ぼーー…………る!」
「ぼーし!」
上のように、”指示役”が掛け声のタイミングを工夫すると楽しくできます。

オモシロルール追加
さらにボクサカバージョンでは、私が当時「坊主頭」だったため、以下のような”オモシロルール”を追加しました。

- 「ボール」と「帽子」を両端に置く
- ”指示役”がプレーヤーの間に立つ
- ”指示役”の掛け声でどちらかにダッシュしてタッチ
- さらに「坊主!」と言ったら”指示役”の坊主頭を「パーン!」と叩く(掴んでも良し)
3パターンできましたね?注意点としては、「坊主!」と言った瞬間、子供の叩く強さで日頃のあなたへの不満の強さが分かってしまうかも知れませんw
まとめ
いかがでしたか?
当時、「親子練習は楽しくないと続かない」という持論があったので、ネット上の情報やサッカー教材などの練習メニューをアレンジしてなるべく面白くできるよう工夫していました。現状足りない能力に対して、一点集中して行えるのも親子練習のメリットです。
ただし、決してイライラして怒ったりすることがないように。子供にとって、親とのサッカーが嫌な時間にならないようにだけ注意しましょう!

∖ライバルが休んでる間にスキルアップ!無料体験実施中♪/