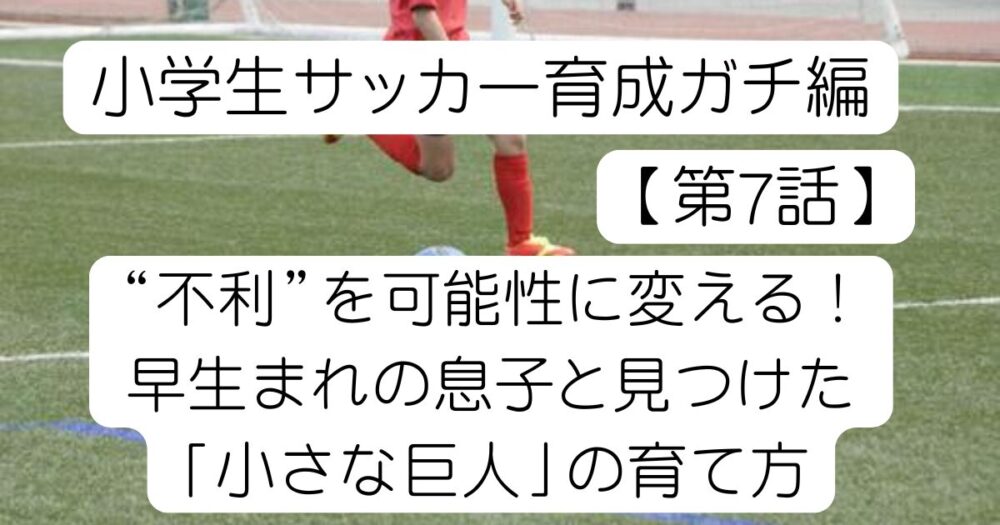小学生サッカー育成ガチ編【第7話】:“不利”を可能性に変える!早生まれの息子と見つけた「小さな巨人」の育て方
こんにちは!
前回の記事では、私たち親子が取り組んできた1対1練習の内容を、具体的にご紹介しました。
単に“ドリブルで抜く”ことを目的とするのではなく、その後のプレーにつながるように考え抜いた練習です。
正直、これまでの中でも特に思い入れの強い取り組みなので、まだ読んでいない方はぜひ目を通してもらえたら嬉しいです。(前回の記事はこちら)
ところで、早生まれのお子さんを応援している保護者の皆さん。
お子さんが高学年になってくると、こんな悩みを抱えること、ありませんか?
実は何を隠そう、我が家の長男も早生まれなんです。
おまけに小学生の頃には成長痛にも悩まされ、大きな大会の選考や強豪チームのセレクションではなかなか結果が出ず、親子で何度も肩を落としたものです…
でも、そんな経験を通して見えてきた大切なことがあるんです。
一見、努力ではどうにもならないように見える体格差も、工夫次第で補えるということ。
そして何より、私たち親の心の持ち方ひとつで、子どもの可能性はもっともっと広がっていくということ。
この記事では、そんな悩みを抱える親御さんの心が少しでも軽くなり、
「よし、また親子で楽しくサッカーと向き合おう!」と、
温かい気持ちで新たな一歩を踏み出せるような、そんなヒントをお届けできれば嬉しいです。
それではどうぞ!

「あの大きい子は評価されてるのに…」早生まれの子を持つ親が抱えるリアルな悩みを解決する”3つ”の方法
冒頭でも少しお話ししましたが、我が家の長男も早生まれということもあり、体の成長は比較的ゆっくりなタイプでした。 それに加えて、小学校中学年から高学年にかけては「シーバー病」に悩まされ、思うように練習ができない日々も続きました。
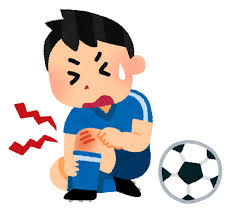
技術的な部分はコーチからも褒めていただけることが多かったのですが、
いざセレクションとなると、やはり体の大きな子やスピードのある子が目立つんですよね。
Jリーグの下部組織や地域の強豪クラブの練習会やセレクションは、残念ながら良い結果には繋がりませんでした。
親子で「またダメだったか…」と肩を落とした帰り道、何度経験したか分かりません。

でもね、そんな経験の中で、ふと気づいたことがあるんです。
それは、「今、自分たちにできることに集中しよう」ということ。
周りと比べて落ち込むのではなく、今の状況でベストを尽くすために何ができるか。
そこで、私たち親子が取り組んだ”3つの方法”をご紹介します。
①栄養管理や体のケア、「できること」に集中する大切さ
「どうせ小さいから…」なんて諦めてしまうのは、本当にもったいないですよ。
もちろん、体の成長には個人差がありますし、それを無理やりコントロールすることはできません。
でも、成長期に必要な栄養をしっかり摂ること、そして体に負担をかけすぎないようにケアすることは、
親としてできる大切なサポートだと思うのです。
我が家でも、食事のバランスには気を配りましたし、睡眠時間もしっかり確保するようにしていました。
あとは、藁にもすがる思い…というと大げさかもしれませんが、
成長期のお子さん向けのサプリなんかも試してみましたよ。
例えば、有名な「ノビルン」なんかも、その一つ。
うちの長男は、牛乳に混ぜて飲むタイプだとすぐに飽きてしまったのですが、
「ノビルン」はおやつ感覚で噛んで食べられるので続けやすいようです。
実はこのノビルン、
「子どもの成長期サポートサプリ部門で3冠達成」、
「子育てママが選ぶ・紹介したいサプリNo.1」、
「口コミ人気No.1」
など、各方面で注目されているみたいです。
「これで急に背が伸びる!」なんて過度な期待は禁物ですが、
「少しでも体の成長の足しになれば」という親心ですよね。
効果のほどは個人差があるでしょうし、あくまでサポートとしてですが、
何か一つでも「子どものためにできることをしている」という安心感は、親にとっても大切です。

②フィジカルに頼らない「体の当て方」「腕の使い方」で、小さな巨人になろう!
さて、体の成長がゆっくりなお子さんにとって、
「どうすれば体の大きな相手と互角に渡り合えるのか?」
というのは、切実な問題ですよね。

スカウトの目も、どうしてもフィジカル的に恵まれた選手にいきがちかもしれません。
でも、諦めるのはまだ早いですよ。
体が小さくても、
「体の使い方一つで、大きな相手をしっかり抑えたり」
「逆に相手の力を利用して有利な状況を作り出したり」
することができるんです。
私がフットサルを”ある決意”をもって復帰した時に(”長男の長男”になるために現役復帰した記事はこちら)
この課題に注目し、自分なりに体や腕の使い方を研究しました。
そうして得た経験値を、長男と共有して習得することに成功。
その経験から言えるのは、
「ただぶつかるだけじゃダメ、賢く体を使おう!」
ということです。
②-⑴ 腕で押さえる~見えない壁を作り出せ!~

体が小さい選手にとって、相手に懐に入られるのは避けたいところ。 そこで重要になるのが「腕の使い方」です。
イメージとしては、自分の腕一本分の「見えない壁」を作る感じですね。
これで相手との間に少しスペースが生まれ、ボールコントロールがしやすくなったり、相手の動きを制限したりできるんです。
息子と練習する時も、
「ただボールを隠すんじゃなくて、まず相手を腕でブロックしてからボールを触ってみようか」なんて言いながら、よく二人でボールの奪いっこをしていました(笑)。

「DFの対して半身状態で、”30秒間”ボールをキープし続けられたら勝ち!」
「腕を使って半身の姿勢でキープしながら、DFの動きを見てターンし、シュートまで持ち込めたら勝ち!」
そんなルールで”勝負”しながら練習を重ね、少しずつ習得していきました。
因みにこのスキル、実は低学年のうちに習得しています。(腕を使ってガツガツ最強選手に勝利した記事はこちら)
②-⑵体の当て方~ぶつかるのではなく、賢く「場所」を支配する基本~

次に「体の当て方」の基本です。
これも、ただ闇雲にぶつかるのではなく、コツがあります。
特に中学生くらいになると、相手のフィジカルコンタクトも格段に強くなります。
ボールコントロールに多少強みがある選手でも、強度が高い相手との試合では簡単につぶされてしまう事も…
耐えるだけの体の使い方だと、腰を痛めたりする原因にもなりかねません。
私が見てきた中でも、体の小さな選手が無理な体勢で相手のプレッシャーを受け続けて、
ケガをしてしまうケースは少なくありませんでした。

だからこそ、早いうちに習得しておくことがおすすめします。
基本的なポイントとしては、
といったことが挙げられます。 こうした基本的な体の使い方をマスターするだけでも、大きな相手に対して有利に立てる場面が増えてきます。
とにかく、後ろから相手のプレッシャーがかかってくる場面では、
DFより先に体を当ててポジションを取ることで、主導権を握れることが多いです。
そして、この「体の当て方」をさらに発展させた、とっておきの技術があるんです。
我が家で密かに「長男スペシャル」と呼んでいる(私が勝手にですが!)、より巧妙な体の使い方をご紹介します。
②-⑶腰を使ったキープ術:相手をいなす小さな巨人の奥義
さあ、ここからは「体の当て方」の応用編。
特に、斜め後ろや横からプレッシャーを受けるような、
相手と角度がある状況で絶大な威力を発揮するのが、「腰を当てる」キープ術なのです。
これは、うちの長男が試行錯誤の末に編み出したテクニックでして、
(たとえ試合でも、思いついた事は絶対に試すことを言い続けた記事はこちら)
体格に頼らずにボールをがっちりキープできる、まさに「小さな巨人」のための奥義とでも言いましょうか。

親の私から見ると、なんだか相手にうまく体でブロックさせて、「当てさせている」ように見えたんです。
でもこれ、実はものすごく計算された、高度な体の使い方なんですよ。ちょっとだけ種明かししちゃいましょうか。
- 相手を“引き込んで”から当てる(受けに回るのではなく、誘い込むのがミソ!)
まず、自分が少しボールを止めるように見せて、相手に「おっ、行けるぞ!」と思わせて近づかせます。でも、これは罠。実際には、腰を斜めにしっかり構えておいて、相手が来た瞬間にグッと“当て返す”準備をしています。 - 体の向きで“侵入角度”を巧みにコントロール(見えない壁、再び!)
ボールと相手DFの間に、自分の腰と片足をスッと斜めに差し込みます。この時の絶妙な体の向きがポイントで、腕を使わなくても「これ以上は寄らせないよ」という、見えないバリアを張ることができます。 - 接触の瞬間に“重心を落として衝撃を吸収”(柳に風、の如く)
腰と足を使って、グッと重心を低く落として衝撃を吸収します。見た目には「当てられても、全然押し戻されていない」状態になるので、ボールが全く動かない。相手にしてみれば、「全力で押したのに、なんで取れないんだ…」と、逆に自分の体勢を崩してしまうことさえあります。 - 当たられた後に“カニ歩き”で微調整(最後の仕上げも抜かりなく)
そして、地味ながら非常に重要なのがこの動き。相手と接触した状態のまま、ボールを隠しながら横方向に半歩、あるいは一歩スライドするんです。まるでカニさんのように(笑)。この細かなステップによって、常に相手との間に適切な距離とスペースをキープし続けることができます。
いかがですか? あまりイメージしずらかった方もいるかもしれません。
要するにこれは、DFに対して体を先に当てる技術の “角度がついた応用版” です。
腰をうまく当てて位置をキープしたり、あえて当てさせる形を作ったりしながら、落ち着いてボールをコントロールするためのテクニックです。
高度なテクニックですが、ボールタッチ練習などと違って習得自体は難しくないと思います。
我が家では、よくメッシ選手や大迫勇也選手のプレーを動画で、「今の体の使い方、すごいね!」「どうやって相手をブロックしてるんだろう?」なんて言いながら、その動きを真似て、ああでもないこうでもないと二人で試行錯誤を繰り返しました。
こうした「体が小さくても戦える術」を小学生のうちから意識して磨いておくことは、必ず将来の財産になります。
いつか体がグンと成長する時期が来た時、そのテクニックが合わさって、とてつもない武器になることでしょう。ぜひ、遊び感覚でチャレンジしてみてください。意外な才能が開花するかもしれませんね。
③本当の勝負は、中学、高校年代から始まる。焦らず、今できることを見つめよう
早生まれのお子さんを持つ親御さんにお伝えしたい、一番大切にしていただきたいメッセージかもしれません。
それは、「小学生時代の評価が全てではない」ということです。

確かに、目の前の試合で活躍したり、選抜チームに選ばれたりすることは、親子にとって大きな喜びですよね。
私も息子の活躍には、いつも胸を熱くしています。 でも、長い目で見ると、本当の勝負は中学生、高校生になってから。もっと言えば、その先もずっと続いていくものなのです。
ジュニア年代で
「あの子はすごい!」
「将来はプロ間違いなし!」
なんて騒がれていた選手が、いつの間にか名前を聞かなくなってしまった…
なんて話、サッカー界では「あるある」なんですよね、本当に。
逆に、小学生の頃はそれほど目立たなかった選手が、中学、高校でグンと伸びて、素晴らしい選手に成長していくケースもたくさん見てきました。
だから、今の体格差や、周りからの評価に一喜一憂しすぎないでいただきたいな、と思うのです。
もちろん、悔しいお気持ちは痛いほどよくわかりますよ。私も何度も経験しましたから。
でも、その悔しさをバネにして、「じゃあ、今できることは何だろう?」と親子で前向きに取り組むエネルギーに変えていけると素敵ですね。
お子さんの成長のタイミングは、誰にもコントロールできません。
でも、サッカーを楽しむ気持ち、上手くなりたいという探求心、そして日々の小さな努力を続けることは、誰にだってできること。
その一つ一つの積み重ねが、いつか必ず大きな力となり、「武器」になるはずです。
親御さんが「うちの子は大丈夫」とどっしり構えて、お子さんの可能性を信じて見守ってあげることが、何より大切なのではないでしょうか。
今の結果に一喜一憂せず、冷静に“本当に勝負すべき時期”がいつなのかを見極めてください。
目の前の評価だけに振り回されず、長い目で子どもの成長を見守ることが、何より大切だと感じます。
親が落ち着いていれば、子どもはちゃんと自分の力で伸びていきますからね。
まとめ
今回は、早生まれで体の成長がゆっくりなお子さんを持つ親御さんに向けて、私なりの経験や想いをお話しさせていただきました。
周りの子と比べてしまって、もどかしい思いをすることも少なくないのかもしれませんね。 でも、そんな時こそ、少し視点を変えてみませんか?
栄養面でのサポートや体のケアといった「今できること」に目を向けたり、体の大きな相手とも渡り合える「賢い体の使い方」を親子で研究してみるのも楽しいかもしれませんね。 そして何より、「本当の勝負はこれからなんだ」と長い目で見て、お子さんの成長を温かく見守ってあげることが大切なのですよ。
サッカーは、体が大きいから、足が速いから、それだけで全てが決まるスポーツではありません。 知恵と工夫と、そして何よりも「サッカーが好きだ!」という熱い気持ちがあれば、必ず道は拓けていくものです。
この記事が、皆さんの心に少しでも温かい光を灯し、「よし、また明日から子どもと一緒にサッカーを楽しもう!」と、そんな優しい気持ちになるための一助となれたなら、これほど嬉しいことはないのですよ。
焦らず、比べず、お子さんのペースを大切に。 そして、親子でサッカーを思いっきり楽しんでくださいね!応援しています。