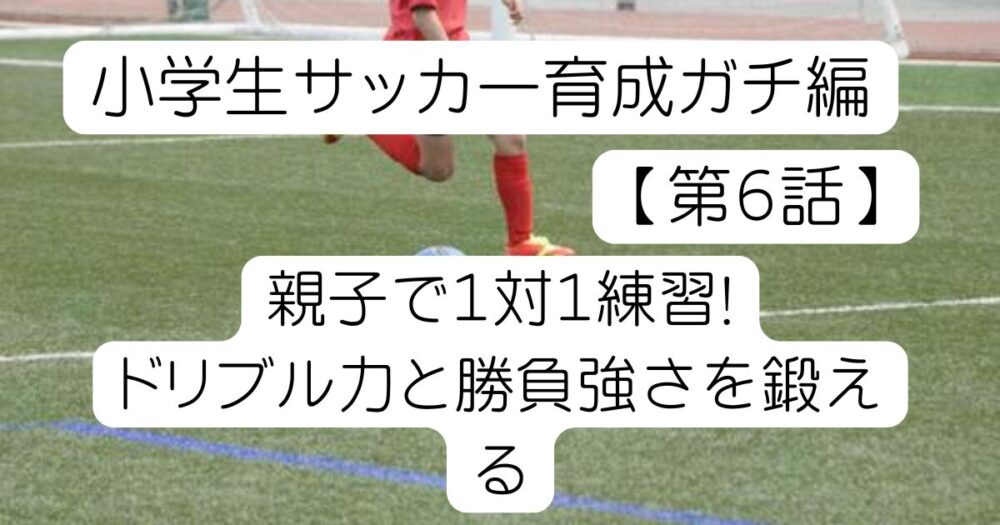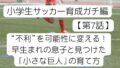小学生サッカー育成ガチ編【第6話】:親子で1対1練習!ドリブル力と勝負強さを鍛える
こんにちは!
以前、スペースへドリブルする感覚を掴み始めた長男の姿をお伝えしましたが、
ボールを持てば、敵のいない場スペースへスルスルと運べるようになり、
少しだけ自信がついたように見えたのです。(スペースを意識したドリブル練習の記事はこちら)
今回は、サイドのポジションを多く任せられることが多くなった長男がサイドでボールを持った時、
目の前の相手ディフェンダーを突破するために、新たなステップとして、
「親子での1対1練習」に取り組むことにしました。
今回は、私たちが試行錯誤しながら楽しく対決しながら見つけた、
単に「抜く」だけではない、その先のプレーに繋がる1対1練習の秘訣についてお話しします。
それではどうぞ!

ドリブルの先にゴールはあるか? 1対1練習の壁
さっそく始めた1対1。しかし、すぐに壁にぶつかりました。
最初は誰もが通る道 – 頭が下がる息子の姿
1対1に慣れていない多くの子がそうであるように、長男も
”相手の動きばかりを気にしてしまい、どうしても頭が下がってしまう”
のでした。
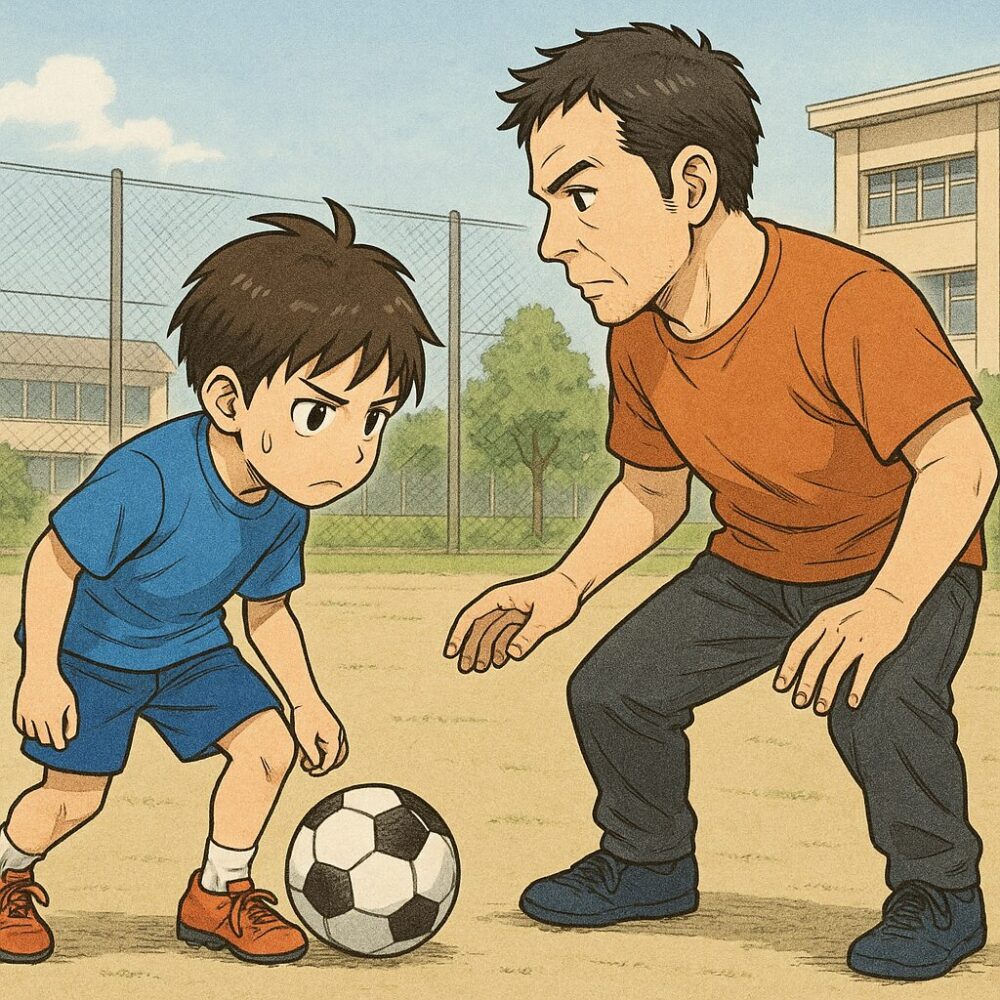
視線が相手に集中しすぎて顔が上がらない。
これでは、周りの状況が見えずらいですよね?
そんなわけで、私が”一休さん”ばりに頭をひねってひらめき、
長男と一緒に取り組んだトレーニングをご紹介します!
「抜くこと」がゴールになってないか? 陥りやすい罠

もちろん、1対1で相手を突破する技術は重要です。しかし、それがドリブルが目的になってしまうと、
その後のプレー、つまり…
という”本来の目的”から遠ざかってしまう危険性があります。

頭が下がって視野が狭いまま、ただがむしゃらに相手を抜こうとする。
たとえ抜けとしても、その先には味方もゴールも見えていない…。
ドリブルという「点」が、ゴールという「線」に結びつかないのです。
実際に、小・中学年代でこの壁にぶつかり、伸び悩んでしまう選手をたくさん見てきました。
「あの子、ドリブルは上手いんだけどね…」
そんな声を聞くたびに、もったいないなぁと感じていたのです。
我が子には、もっと選択肢を広げてあげたいな。
そしたらよりサッカーが楽しくなるだろうなと感じました。
そこで、以下のような作戦を実行することに。
我が家流「スペース意識」の1対1 – 目的は突破の先にある
幸いなことに、長男は低学年の頃から、
1対1よりも先にスペースを意識したドリブル(スぺースを意識した練習の記事はこちら)を練習してきました。
この経験が、今回の1対1練習で大きなヒントを与えてくれたのです。
敵は「ついで」に見る感覚 – 背後のスペースを意識する
私たちが徹底したのは、「目の前の相手」ではなく、
常に「相手の背後にあるスペース」を意識することでした。

相手の背後にあるスペースを意識してみよう!
相手は”ついでに目える”くらいで良いよ♪
最初は戸惑っていた長男ですが、試しに、まず普通に1対1をやり、
次に背後のスペースを強く意識して同じことをやってみました。
すると、不思議なことが起こります。
スペースを意識した方が、
ボールを運ぶコースが自然とディフェンダーから遠い、取られにくいコースを通る
ようになったのです!

目の前の相手に集中しすぎると、どうしても直線的な動きになりがちですが
スペースを意識することで、より”効果的なルート”を選択できるようになる。
これは大きな発見でした。
頭も自然と上がり、相手は「ついでに見える」ような感覚。私たちが目指していたものでした
「抜いて終わり」じゃない! ゴールを意識する
スペースを意識し、少しずつ顔が上がるようになった長男。
しかし、本当の勝負はここからです。
「抜く」ことはあくまで手段。
その先に待つ「ゴール」という目的を見失ってはいけません。

ところで長男くん。サッカーで一番大事な、最終的な目的はなんだっけ?

ゴ……

はい!ゴールで~す!

……今、言おうと思ってたのに
……ていうか、なんかこのやり取り、前にもあったような……
(前にもあったやり取りの記事はこちら)
そこで、1対1の練習も、ただ相手をかわすだけでなく、必ず「ゴールを奪う」こと、
ゴールできたら、勝ち!シンプルなルールがですが大事な事だと感じます。
実践!ボクサカ流・状況別1対1トレーニング
具体的にどんな練習に取り組んだのか?
ここでは、特に課題となりやすい「サイドでの突破」を想定し、当時よく行っていた練習メニュー(※左サイドを例に)をいくつかご紹介しましょう。もちろん、これらの練習は右サイドでも同様に行います。
サイド攻略! 3つの仕掛けパターン
左サイドでボールを持った状況を想定します。
目の前には相手ディフェンダー。
ここからどうやってゴールを目指すか?

我が家では、主に”3つのパターン”で仕掛ける練習をしました。
(イメージしやすいように動画も添えてご紹介します。)
軸足リードで仕掛ける(駆け引きの練習)
これは、軸足を前に出しながら進みつつ、利き足(長男は右足)の内側でボールに触れて仕掛けていく動きです。
特にサイドのタッチライン際では効果的で、フェイントや重心移動を入れやすく、相手の動きにも柔軟に対応しやすいのがポイント。
実際にやってみて感じたことは、以下のような点です。
相手と横並びになった瞬間に“反発ステップ”を入れると、ネイマール選手や三笘選手のような縦突破も狙えるようになります。ボールが足から離れずらいので、相手との駆け引きの練習に非常に有効。
相手に向かっていく仕掛け(相手を止める練習)
次の段階では、“相手に向かっていく”仕掛け方にチャレンジ。
サイドからボールを持った状態でDFに対して、斜めに少し角度をつけて仕掛けていきます。
イメージとしては、ウィンガー時代のソン・フンミン選手がサイドからDFに斜めにアタックし、シザースでタイミングをズラして縦に突破するドリブルが近いと思います。分かる方がいなかったら申し訳ない…
利点としてはスピードを保ったまま仕掛けることが出来ること。
たとえば、足の速さに自信がある選手が、そのスピードだけで抜けてしまうタイプだと、そのままのスタイルで中学年代まで成長してしまうケースがよくあります。
でも、そこでよく起きるのが
「こいつ、縦しかないぞ」って読まれて、手を切られた瞬間に何もできなくなるパターン。
並走されただけで選択肢がなくなってしまうような、“あるあるな壁”にぶつかるんですよね。
だからこそ、そんな選手に身につけてほしいのが、この“向かっていくドリブル”。
相手の動きを止めて、駆け引きの主導権を握れるようになれば、スピード頼みの突破から、一段上の突破へと進化できます。軸足リードよりコントロールが難しいですが、相手を止めるということを理解する”きっかけ”づくりにも有効だと感じました。
ケースバイケースではありますが、右利き・左サイドの場合、
相手の右足側(=相手の外側)に仕掛けていくと、中へのカットインも縦への突破も狙いやすくなります。※右利き右サイドでも同様です。
“抜ける角度を自分で作れる選手”になれるってことです。
こちらが駆け引きの主導権を握りやすくなるので、ぜひ一度試してみてくださいね♪
静止した状態から正対して仕掛ける(飛び込ませない練習)
試合中、パスを受けて一度動きが止まり、相手と正対する場面は意外と多くあります。
この状況からどうやって相手を突破するか。これが本当に難しい……
しかし、メッシ選手のように、実際の試合で抜き去るまでいかなくても、
この練習をしたことによって、試合のちょっとした場面でこの練習が活きていると感じます。
焦ってボールを動かすのではなく、まずはしっかりと自分のコントロール下に置くこと。
そして、相手の重心や動き出しを観察し、簡単に飛び込ませない“間合い”を作る。
この“間”を作れるかどうかが、駆け引きの練習になるんですよね。
※↓の動画の冒頭シーンと同じ状況を再現して、子供と実際に対決してみます。
やってみると、これがなかなか面白いんですよ♪
正面突破への布石 – 角度を作る意識
次に練習したのは、ゴール正面、ただし相手と少し距離がある状態からの1対1。
カウンターからの1対1の様な場面を設定しました。
正面から相手を抜くというのは、サイドから仕掛けるよりもさらに難易度が上がります。
これは、私自身がオジサンになってスピードでちぎれなくなったフットサルで、身をもって痛感した部分でもあります(笑)
ここでのポイントは、「いきなり直線的に仕掛けない」こと。

真正面って、抜くのむずかしいよな。
だから、まずは少し斜めに動いてみよう。
相手に対して角度をつけると、自然と相手の体の向きも変わるから仕掛けやすくなるよ。
ちょっとやってみようか。
ちなみに私のクセは、足裏で横にズラしてからのシザース。
一方で長男は、インサイドやアウトサイドでズラして角度を作りつつ、ボディフェイントを混ぜて仕掛けるスタイルです。
そして、上でご紹介したように「相手に向かって仕掛けていく」という手法も効果的。
相手に対してどちらかにズラすことで逆を取りやすくなります。
「ズラす」ことについては、以下の動画が参考になりやすいと思いました。
相手の対して、どちらかに”ズラして”角度を作ってから、相手の逆を取る。
こうした練習を通じて、長男は単にボールを扱う技術だけでなく、
駆け引きや状況判断の大切さも少しずつ理解していったように思います。
もちろん、すぐに全部うまくいくわけではありません。
ボールを奪われて悔しそうな顔をすることなんて、むしろ日常茶飯事。
それでも、親子で一緒にゴールを目指し、試行錯誤を重ねた時間は、私たちにとってかけがえのない財産です。
まとめ: 1対1の壁を越える鍵は「スペース」と「ゴール」意識
今回は、親子で挑んだ「1対1」練習の試行錯誤についてお話ししました。
単に相手を抜く技術だけでなく、「相手の背後のスペースを意識すること」、そして常に「ゴールという最終目的を見据えること」。この2つを徹底したのが、我が家流の練習のポイントでした。
サイドでの仕掛けや正面からの崩しなど、具体的な練習もご紹介しましたが、何より大切だったのは、親子で「なぜ?」を考え、失敗からも学びながら一緒に挑戦した過程そのものだと感じています。
「抜く」ことから「スペースを使い、ゴールへ繋げる」意識へ。息子のプレーが少しずつ変化していく様子は、親として大きな喜びでした。
お子さんの成長に寄り添い、一緒に楽しむこと。それが一番の近道かもしれませんね。