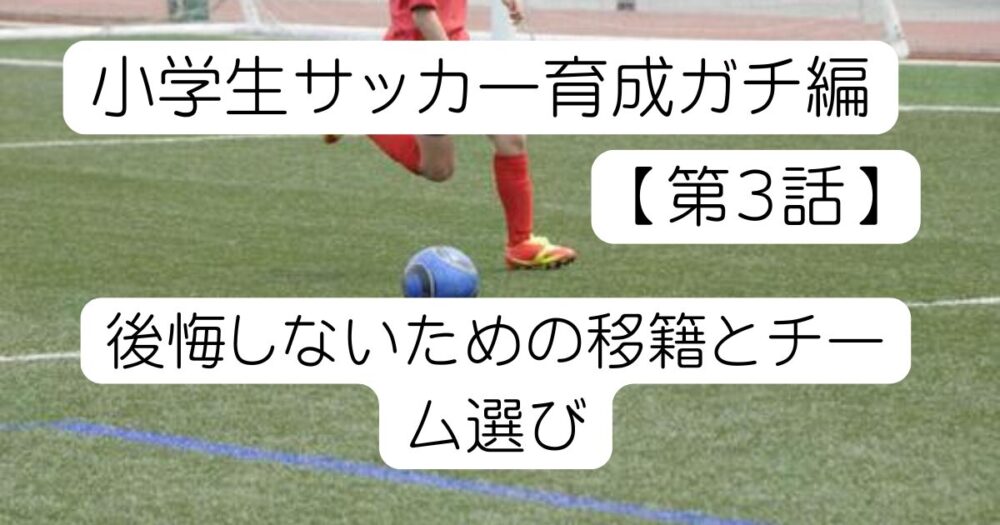小学生サッカー育成ガチ編【第3話】:後悔しないための移籍とチーム選び
こんにちは!
前回は、我が家の経験談を交えながら「移籍を考えるタイミング」についてお話ししました。前回の記事はこちら
担当コーチとの相性やプレーの制限によって笑顔を失った長男。しかし、仲の良い友達と離れたくない気持ちもあり、なかなか決断できずにいました。
そんなある日、長男が突然「俺、辞める」と口にしたのです。
そこからは、驚くほど早く話が進みました。
今回は、チームを辞めたあと、どのように移籍先を探したのか…
実際の経験をもとにご紹介していきます。
それでは、どうぞ!

小学生サッカー移籍|後悔しないチームの選び方【実体験から】
チームを辞めることは、当日まで誰にも伝えずにいました。長男が「言わなくていい」と言ったので…
いざ当日、伝えに行くと、保護者の方々はさすがに驚いていましたが、
それでも、すぐに「長男の気持ち、わかるよ」と共感してくれる方がほとんど。
長男も、チームメイトたちに囲まれながら「辞めるなよ…」なんて言ってもらい、
あとから聞くと、泣きそうになっていたようです。
やっと居場所ができて、友達もたくさんできたチーム。
そこから現実に離れるとなると、長男だけでなく、親である私も胸がいっぱいになりました。
しかし、原因となったあのコーチは割とあっさり、こう言いやがったのです。

え?…そうですかー…では後日手続きを~
アノヤロ~…
子供が本当に目指したい姿を聞いてから|最適なチーム選びとは?

チームを辞めたあと、私が最初に長男に対してとった行動と、やり取りはこんな感じでした。
まずは、ひとまずサッカーから離れて心の回復を優先。(気晴らしに外出するなど)

そのうえで、
- サッカーをまだ続けたいかを聞く
- どうなりたいかを聞く
- その目標に合ったチームを探すため、どんなチームに行きたいかを聞く
- そのチームに行ってどうしたいかを聞く
という順番で、長男の気持ちを一つずつ確認。
幸いなことに、長男のサッカーへの情熱はまだ消えていませんでした。
むしろ、辞めたことでわかったのは「精神的な切り替えが意外と早い」ということ。
すでに次のステップに意識が向いていたのです。
以下は、③からの具体的なやり取り。

そっか、サッカー続ける気はあるんだね!
お父さんは、笑って楽しくサッカーしてる長男くんが見たいから、
自由にできそうなチームなら、レベルが多少落ちても全然かまわないと思うよ。
長男くんは、どうなりたい?

う~ん…サッカー選手。

(子供は大体そう言うよね~w)
じゃー、
どんなチームが良い?
そのチームでどうしたい?

自由に出来て強いチーム!
前のチームと戦ってやっつける!

ほ~!(ちょっと意外だった)
じゃあ、自由にできて、前のチームとも戦えそうな強いチームを探そう!
ちなみにあえて”ふわっ”とした感じで聞きました。
「親の感情(無意識に誘導しないように)が入らないため」と「長男の中で、すでに出ているであろう答えを自分で出してもらうため」です。※コンサル業の方に教えてもらった”オープンクエスチョン”という手法を、当時の長男仕様にアレンジしています。
意外だったのは、戦術や勝利へのこだわりが強すぎて自由が奪われたことが原因で辞めたのに、
次に選びたいチームが「強豪チーム」だったこと。
子供って、本当にオモシロいですね!
ということで、長男の目標は
「自由にできて、かつ強いチームで前チームにリベンジする」

これを達成できそうなチームを探します。
一見、矛盾していて難しそうですが、要するに…
これらの条件を満たすチームを、送迎できる範囲で探すことにしました。
チーム探しは現場で決める|小学生サッカー移籍体験記

今なら、ホームページだけでなくSNSなどからもチーム情報を確認できます。
ですが、必ず実際に体験してみることをおすすめします。
できれば、一度だけでなく複数回体験した方が、失敗も少なく済むと思います。
(なぜか1回までとか2回までとか制限されているチームが多いですが…)
というのも、ホームページやSNSはあくまで集客目的。
見栄えを良くしていることも多く、ジュニアサッカー界では「入ってみたら全然違った」なんてことが普通にあるからです。

我が家の実例|期待して体験に行ったけれど…
たとえば我が家の場合。
家の近くで、「 ”某超強豪高校に進みプロになった選手” を輩出したチーム」を見つけました。
私自身も知っていた選手だったので、興味を持ちホームページを覗いてみると、
チームの理念にこう書かれていたのです。
「ドリブルや子供の個性を大事にしています。」
まさに長男の移籍先にピッタリだ!と期待して、すぐに体験を申し込みました。
ところが…
実際の練習内容は、決まった形をひたすらこなしていくスタイル。
自由な発想を促す雰囲気はなく、体験後の長男も「つまんなかった」とポツリ。

希望を抱いていた分、なんとも残念な結果に終わりました。
保護者に直接聞くのが一番確実
ちなみに体験時、隣にいた保護者の方に、さりげなくチームの雰囲気を聞いてみたんです。

月謝や練習時間、場所などいろいろ教えてもらった後、
一番気になっていたことを聞いてみました。

チームのホームページに、“ドリブルや子供の個性を大事にしています”って書いてありましたけど、実際どうなんですか?

え?そ、そうなんだ~…ハハ…
という反応。
その瞬間、「あ、実態は違うんだな」とすぐに察しました。
後日、以前そのチームに在籍していたという選手の保護者から、
「結果を求めるようになってから、方針が変わってしまった」と聞き、そういうことか、と納得。
当然、候補から外れることになります。
チーム選びでは「保護者の雰囲気」も重要
子供のサッカーは、親も深く関わる場面が多くなります。
だからこそ、実際に体験に行ったときに、保護者同士の雰囲気や人間性を感じ取ることも大事だと思います。
表面的な情報だけに惑わされず、
子供にとっても親にとっても「ここで頑張れそう」と思えるチームを探していきましょう。
まとめ|「子供主体」でチームを選ぼう
サッカーチームの移籍は、子供にとっても親にとっても大きな決断です。
特に小学生年代は、サッカーそのものへのモチベーションを大きく左右するタイミングでもあります。
今回、我が家が実感したポイントは、
- まず子供自身の気持ちをしっかり聞くこと
- 実際に体験して、チームの「生の空気感」を感じ取ること
- 表面上の情報に惑わされず、保護者や子供たちのリアルな雰囲気を確かめること
この3つでした
情報収集はもちろん大事ですが、それ以上に「現場で感じた直感」も信じるべきだと思います。
子供が自然に笑顔になれる環境。
そして、親も安心して見守れる環境。
もちろん、100%理想通りのチームなんて存在しません。
だからこそ、この記事で紹介した「子供の目標に沿ったチーム選び」を基準に、
”譲れない部分”
”ある程度受け入れるべき妥協点”
を整理しながら考えていきましょう。
そして何より子供のサッカー人生は、子供自身のもの。
大人の都合だけで選ばず、子供の「こうなりたい」という気持ちを大切にしてあげたいですね。

高学年になってからの移籍は、チームの雰囲気や保護者同士の関係がすでに固まっていることも多く、なかなか難しくなりがちです。
移籍を検討するなら、4年生くらいまでに動くのがおすすめですよ♪