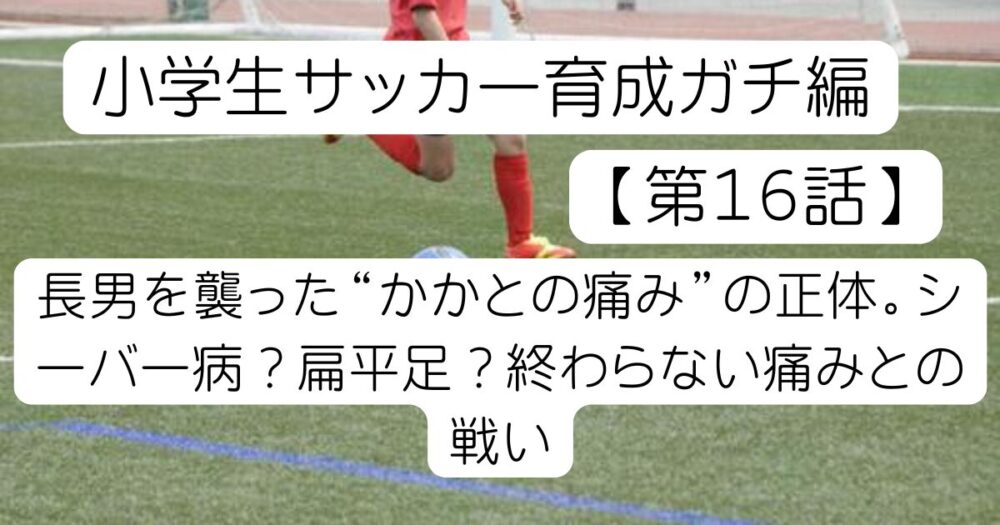小学生サッカー育成ガチ編【第16話】:長男を襲った“かかとの痛み”の正体。シーバー病?扁平足?終わらない痛みとの戦い
こんにちは!
前回の記事で、順風満帆だった長男のチームが、様々な要因で少しずつ歯車が狂い始めたお話をさせていただきました。そして、その物語の最後に、長男自身の体にも異変のサインが現れ始めたことを、少しだけお話ししましたよね。(前回の記事はこちら)
「パパ、なんだか最近、かかとが痛いんだ…」
最初は、練習のしすぎかな、なんて軽く考えていました。男の子なら誰でも経験する、いわゆる「成長痛」のようなものだろう、と。
でも、それは、これから長く続く、痛みとの苦しい戦いの始まりの合図だったのです。
この記事では、小学生のサッカー選手を襲う「かかとの痛み」について、我が家の長男が実際に経験した、終わりの見えない通院の日々、そして明らかになった痛みの本当の原因、そして親として感じた無力感について、正直にお話しさせていただきたいと思います。
もし今、同じような痛みでお子さんが苦しんでいたり、親としてどうしてあげるべきか悩んでいる方がいらっしゃいましたら、この記事が「うちだけじゃなかったんだ」と、少しでも心を軽くするきっかけになればと願っています。
それではどうぞ!
最初の診断は「シーバー病」。でも、なぜ治らない?~終わらない通院の日々~
長男が小学5年生になったあたりから、その痛みは始まりました。最初は練習後に少し痛む程度だったのが、次第にプレー中にも顔をしかめるようになり、「これは一度、専門の先生に診てもらおう」と、私たちは近所の整形外科の門を叩きました。

そこで告げられた診断名は、「シーバー病(踵骨骨端症)」。
先生曰く、かかとの骨の端っこにある、成長するための柔らかい部分(成長軟骨)が、ふくらはぎの筋肉やアキレス腱に強く引っ張られることで炎症を起こしてしまう、まさに成長期の、特にサッカーやバスケットボールなど、走ったり跳んだりするスポーツをしている男の子によく見られる痛みだということでした。
原因が分かったことで、私たちは少しだけ安堵しましたが、その安堵は、長くは続きませんでした。
整形外科で勧められた電気治療やマッサージ、湿布といった処置は、正直なところ、その場しのぎの効果しかなかったんです。(※個人差があるのかもしれません…)
治療した直後は少し楽になるようなのですが、練習をすればすぐに痛みがぶり返す。その繰り返し。

私たちは、少しでも良くなるならと、腕が良いと評判の接骨院を探し、保険対象外の自費治療も試してみました。ですが、それでも一向に改善に向かう兆しは見えなかったのです。
痛みの“本当の犯人”は一人じゃなかった!~長男の足に隠されていた複数の要因~
いくつかの病院や接骨院を巡り、様々な先生方の診断内容から、一つの答えにたどり着きました。
それは、長男のかかとの痛みの原因は、単に「シーバー病」という一つの病名で片付けられるものではなく、
彼の体の特徴や、サッカーという環境がもたらす、複数の要因が複雑に絡み合っていた、ということです。
- 犯人候補①:「扁平足(へんぺいそく)」という足の個性
長男の足は、いわゆる「扁平足」で、土踏まずのアーチがほとんどありませんでした。この土踏まずというのは、地面からの衝撃を吸収してくれる、体にもともと備わっている優秀なクッションなんです。そのクッション機能が弱いと、走ったりジャンプしたりするたびに、地面からの衝撃がかかとにダイレクトに「ドスン!」と伝わってしまう。 これが、かかとの成長軟骨に大きな負担をかけていた。 - 犯人候補②:「筋肉が硬い」という体の状態
長男は、体の柔軟性、特にふくらはぎや太ももの裏の筋肉が、昔から非常に硬いタイプでした。ふくらはぎの筋肉が硬いと、その先にあるアキレス腱を常に強く引っ張ってしまいます。そして、そのアキレス腱は、何を隠そう、痛みの震源地であるかかとの骨にくっついている。つまり、ガチガチの筋肉が、常にアキレス腱を通じてかかとの骨をギリギリと締め上げていた、というわけです。 - 犯人候補③:やっぱり「サッカーのしすぎ」という現実
そして、身も蓋もない話ですが、単純に「使いすぎ(オーバーユース)」という現実もありました。チームでの練習、自主練、そして試合。サッカーが大好きな彼にとって、ボールを蹴らない日はないくらいでしたから、成長期のデリケートな足に、相当な負担がかかっていたことは間違いありませんでした。
一つの症状でも、その原因は決して一つではない。この当たり前の事実に気づくまで、私たちは随分と遠回りをしてしまったのです。

親子で挑んだ改善策と「継続の壁」~床に転がるタオルの思い出~
原因が複数あるのなら、アプローチも複数試してみよう!そう考えた私たちは、先生方から教わった改善策に、親子で取り組んでみることにしました。
代表的なのが、扁平足の改善に効果があると言われる「タオルギャザー」という足の指の体操です。床に広げたタオルを、足の指の力だけで「くしゅくしゅ」と手前にたぐり寄せる、あのアレです(笑)

「よし、毎日お風呂上がりに一緒にやろうぜ!」
初日は、私も長男も意気込んで挑戦しました。しかし…これが、地味で、退屈で、なかなか続かない(苦笑)。
「パパ、今日これやるの…?」
日に日にテンションが下がっていく長男。
そして、気付けば「”一人”タオルギャザー(笑)」

これでは意味ないと、ストレッチも一緒にやってみましたが、残念ながら、彼の痛みが劇的に改善することはありませんでした。
子供に、痛みがすぐには消えない地道なトレーニングを毎日継続させることの難しさ。
これは、多くのお父さん、お母さんが直面する、大きな「壁」なのではないでしょうか。
頭ではその重要性が分かっていても、子供のモチベーションを維持し続けるのは、本当に根気のいることです。
痛みと共に戦った6年生~ハラハラしながら見守った、大事な時間~
結局、このかかとの痛みとの戦いは、長男が小学校を卒業するまで、ずっと続くことになりました。
特に、彼のサッカー人生にとって、本当に大事な場面で、その痛みは容赦なく顔を出しました。
まさに大事な時に限って、痛みが強く出てしまう。
試合中や選考中に不意にかかとを踏まれただけで、顔を歪めてプレーが続けられなくなってしまう…。
6年生の時の試合は、正直、純粋な気持ちで応援できた記憶があまりありません。
プレーの一つ一つに、心の中では「どうか、かかとが痛みませんように…」と、常にハラハラしながら祈るような気持ちで見守っていました。親として、これほど歯がゆく、もどかしいことはありませんでした。
まとめ:終わらない痛み、そして中学で訪れた「新たな戦い」へ
小学生の間、私たちは長男のかかとの痛みを、完全に克服させてあげることはできませんでした。これが、私たちのリアルな結末です。
でも、この痛みとの戦いは、決して無駄ではなかったと、今なら思えます。
長男は、この経験を通じて、自分の体と深く向き合うことの大切さ、そして、日々のケアやコンディショニングの重要性を、誰よりも身をもって学んだはずです。それは、これから長くサッカーを続けていく上で、何物にも代えがたい貴重な財産になったと信じています。
そして、物語はまだ終わりません。
中学に上がった長男を待っていたのは、かかとの痛みの改善…ではなく、今度は痛みの場所が「膝」へと変わっていくという、新たな戦いの始まりだったのです。「え、次は膝なの!?」と、私たち親子は再び頭を抱えることになります。
しかし、この新しい痛みが、結果的に、私たち親子を長年苦しめてきた「足の問題」の根本的な原因を突き止め、そして劇的な改善へと導いてくれる、大きな大きなヒントになるなんて、この時の私たちは知る由もなかったのです。
その、長いトンネルの先にようやく見えた一筋の光のお話は、また次回の記事で、じっくりとさせていただきたいと思います。

この頃の私は、長男のことが心配で心配で、
まるでアニメ「ち○○子ちゃん」でおなじみの「ポマ〜ン…」という効果音とともに、顔に縦線が入っていたかもしれません(笑)