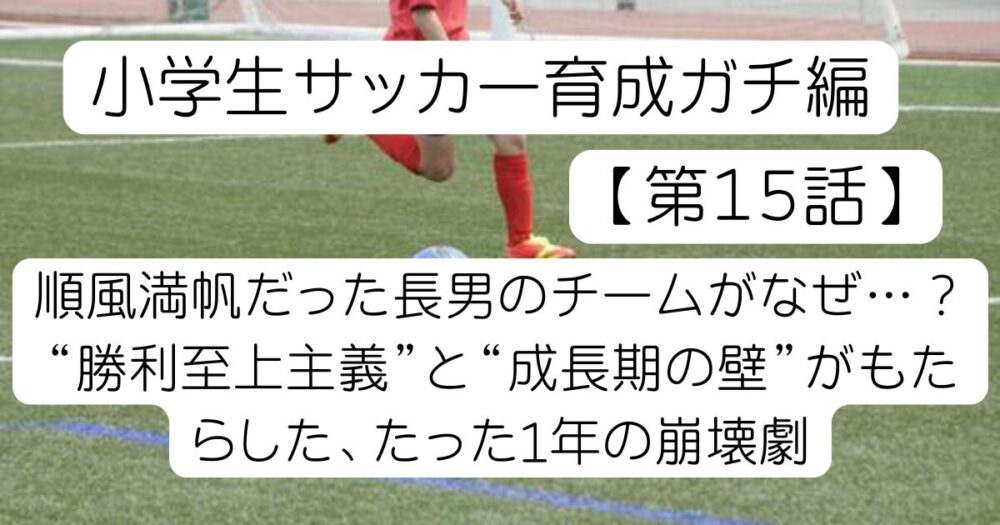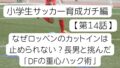小学生サッカー育成ガチ編【第15話】:順風満帆だった長男のチームがなぜ…?“勝利至上主義”と“成長期の壁”がもたらした、たった1年の崩壊劇
こんにちは!
お子さんのサッカー人生、順風満帆な時もあれば、まるで突然嵐がやってきたかのように、暗雲が立ち込める時もありますよね。
「あんなに楽しそうだったのに…」
「あんなに強かったのに…」
チームや我が子の変化に、心を痛めたり、戸惑ったりしている親御さんもいらっしゃるかもしれません。
我が家の長男も、4年生の頃はまさに絶頂期でした。
新しいチームで自分の居場所を見つけ、
サッカー選手として、そして一人の少年として、キラキラと輝く日々を送っていました。
このまま順調に、彼のサッカー人生は続いていくのだろうなと、親として信じて疑いませんでした。
しかし、5年生になったあたりから、彼の、そしてチームの歯車が、少しずつ、しかし確実に狂い始めたのです。
今日は、そんな我が家が経験した、「順風満帆」から「崩壊」への、ちょっぴり苦い物語をお話しさせていただきたいと思います。
この記事が、同じように子供の成長の壁やチームの変化に悩む親御さんにとって、何かを考え、次の一歩を踏み出すための、小さなきっかけになればと心から願っています。
それではどうぞ!
順風満帆だった4年生~自信に満ちた日々~
長男が4年生の時に移籍したチームは、県内でもある程度実績のある、高いレベルを目指す素晴らしい環境でした。
そこで彼は、素晴らしいコーチと仲間たちに出会いました。

指導者からの信頼を一身に受け、彼はみるみるうちに中心選手として成長。
メンバーにも恵まれ、チームは数々の大会で好成績を残していきました。

ある大会の決勝戦では、相手チームが長男に対して2人がかりでマークについてくるほど。
それでも果敢に挑んでいくその姿に、親の私も胸が熱くなったものです。
まさに、「順風満帆」という言葉が、彼とチームのためにあるかのような、そんな幸せな時間でした。
忍び寄る影…TOPチームの“勝利至上主義”がもたらした歪み
そんな輝かしい日々が、永遠に続くかのように思えた5年生の頃。
少しずつ、チームの空気に変化が訪れ始めたのです。
その発端は、一つ上の学年であるTOPチーム(6年生)の不振でした。
TOPチームは、とにかく結果にこだわり、『走るサッカー』をチームの看板として掲げていました。
前線の選手もゴール前から徹底的に守備をし、格上チームとの技術的な差を、圧倒的な走力で補うというスタイル。

もちろん、勝利を目指すことは素晴らしいことですし、ハードワークは現代サッカーの基本です。
でも、それが小学生年代の子供たちの、心身の発達段階や個性を無視したものになってしまうと、そこに歪みが生まれてくるのかもしれません。
TOPチームの成績が思うように上がらなかったからでしょうか、
監督の目は、一つ下の学年である長男たちの代の、特に中心選手たちに向けられるようになりました。
週末になると、長男のチームメイトたちが、TOPチームの試合に呼ばれるようになったのです。
(※幸か不幸か、長男は移籍した時期が遅く、トップの指導者にはあまり認知されていなかったようで、その招集を免れたのですが…今思えば、それが彼の選手生命にとっては幸運だったのかもしれません。)
崩壊への序曲~ストライカーの離脱と、自信を失う仲間たち~
そして、恐れていたことが起こってしまいました…
TOPチームの試合に頻繁に呼ばれ、その「走るサッカー」の中で酷使されていたチームメイトの一人…
チームで1、2を争う得点率を誇っていたエース格の選手が、腰椎分離症という、アスリートにとっては非常に深刻な怪我を負ってしまったのです。

成長期の子供の体にかかる、過度な負荷。
結果を求めるあまり、子供たちの未来よりも、目先の勝利を優先してしまった結果と言えるのかもしれません。
その後、彼はチームを去ることになってしまいました。

チームにとって、最大の得点源を失ったことは、計り知れない痛手でした。
勝利という一つの目標が、子供たちの「未来」や「サッカーを楽しむ心」を犠牲にしてはいけない。
当たり前のことのはずなのに、その当たり前が、いとも簡単に崩れ去る現実を、私は目の当たりにしました。。
重なる不運の連鎖~“成長期の壁”と、長男に芽生えた痛みのサイン~
ストライカーの離脱をきっかけに、チームの歯車はさらに狂い始めました。
長男の学年は、早生まれの子が多く、全体的に小柄な選手がほとんど。
4年生の頃は、その技術と連携で体格差をカバーできていましたが、5年生、6年生と学年が上がるにつれて、相手チーム、特に強豪とのフィジカルの差は歴然となっていきました。(体格差がある相手に対抗する技術をご紹介している記事はこちら)

大きい選手が多い強豪チームに、どうしても最後のところで競り負け、勝ちきれず負けてしまう。
(まあ、我が家の場合、長男が楽しめてさえいれば、勝敗はあまり気にしていませんでしたが(笑))
そして、そんなチーム状況の中、ついに長男の体にも異変のサインが現れ始めたのです。
「パパ、なんだか最近、かかとが痛いんだ…」

最初は、練習のしすぎかな、くらいに軽く考えていました。
ですが、その痛みは日によって強くなったり弱くなったりと、波があるようで、彼のプレーにも明らかな影響が出始めまていたんです。
以前のようなキレのある動きが見られず、どこかプレーに集中しきれていない。
指導者の交代劇、ストライカーの離脱、自信を失う仲間たち、越えられない体格の壁、そして、長男を襲う謎のかかとの痛み…。様々な要因が、まるで負のスパイラルのように重なり合い、あれだけ強かったチームは、たった1年で、「勝てないチーム」へと変わってしまっていたのです。
まとめ:崩壊から見えた問題点と、次への希望の光
たった1年で、順風満帆だったチームが崩壊していく過程を間近で見てきて、私はそこに横たわるいくつかの根深い問題を痛感しました。
強かったチームが、勝てないチームになってしまった。
それは、親としても、そして何より子供たち自身にとっても、辛く、苦しい経験でした。
でも、この経験は、私たち親子にとって、そして長男のサッカー人生にとって、決して無駄ではなかったと、今なら断言できます。
困難な状況の中から何を学び、どうやってそれを乗り越えていくのか。そのプロセスこそが、子供を、そして私たち親をも、本当に強くしてくれるのですから。
あの輝かしい日々から一転、チームは苦しみ、長男の足には痛みが走る。
でも、物語はまだ終わりません。
むしろ、ここからが、私たち親子の新たな挑戦の始まりでした。
そのお話は、また次回の記事で、じっくりとさせていただきたいと思います。