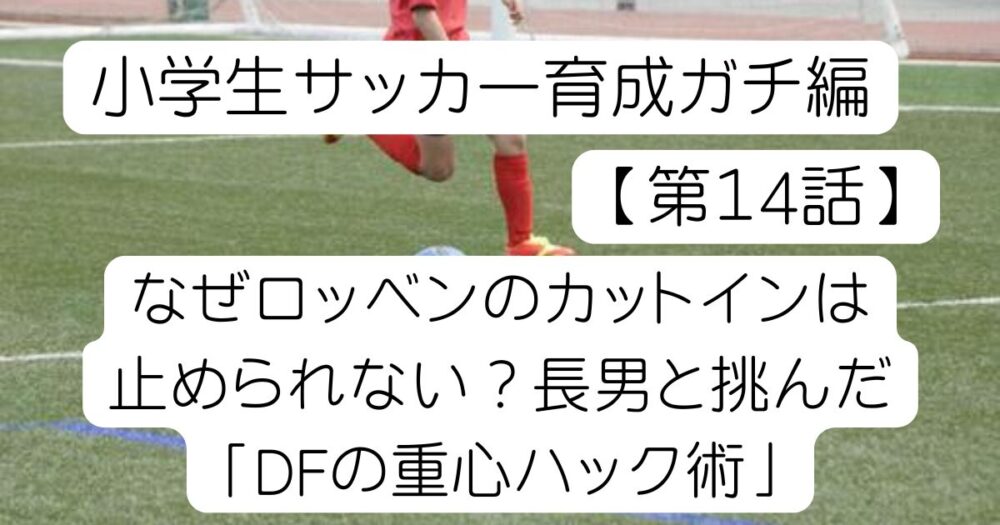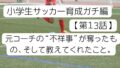小学生サッカー育成ガチ編【第14話】:なぜロッベンのカットインは止められない?長男と挑んだ「DFの重心ハック術」
こんにちは!
ところで「これだけは誰にも負けない!」
という、得意なドリブルの形、必殺の武器、あなたのお子さんにありますか?
サイドからカットインしてシュートを狙う形、相手の逆を突く鋭いターン、あるいは、誰も想像しないようなトリッキーなフェイント。
自分だけの武器があるって、本当に素晴らしいことだし、サッカー選手としての大きな自信になりますよね。
我が家の長男も、小学生の頃から得意な武器を持っていました。
彼は右利きなのですが、左サイドから中へ切れ込んでいく「カットイン」が好きでよく試合で披露していました。
いわゆるクセに近いような感覚で。
今回は、私たちのちょっぴりマニアックで、でもちょっと面白い
「得意技のロジカル深掘り大作戦」をご紹介いたします。
この記事では、長男が「感覚」だけでやっていたカットインを、その裏にある「理論」で解き明かし、誰も止められない「必殺技」へと進化させていった、我が家の親子の物語をお話ししたいと思います。
それではどうぞ!
「なぜ抜ける?」の謎を解く鍵は“相手の足元”にあった!~DFの重心ハック術~
小学3年から、カットインが大好きすぎる長男。
それは、もはや”クセ”と言っても良いくらいでした。
当時のままでも、充分成功率は高かったのですが、感覚でやっている部分が強かったのです。
もちろん、感覚やタイミングも大事ですが、またもや実験大好きな私の”変態クセ”が顔を出してしまいました。
というか、私が長男のようにカットインを上手くなりたかったのです(笑)( ´∀` )ダッテカッコイイジャン
そこで、思いついたのが
ついでに、「カットインをロジカルに深掘り」してみたら、どんな発見があるのか…
そんな想いから、「カットインマスター」ことロッベン師匠のプレーを、何度もスロー再生したりして分析。
さらに、さまざまな「カットインのハウツー動画」なども参考にしながら、自分なりに理論を構築していきました。
そして、「もしかして、こうなんじゃないか?」という仮説を立て、1対1の場面を中心に、実験的なアプローチを試してみたのです。

ロッベン流・おとりのドリブル!DFを“縦”に誘い出すボールタッチ
「なぜ、あのカットインは止められないのか?」
あれこれと考えた末にたどり着いた、ひとつの答えがあります。
それは、“カットインそのもの”ではなく、その直前に行われる「おとりのドリブル」にこそ、最大の秘密があるのではないか、という仮説。
華麗な必殺技の裏には、必ず巧妙な「布石」がある。
そのカラクリを、ボクサカ流に解き明かしていきましょう!
【ボクサカが熱血解説!このテクニックのタネと仕掛け】

あの魔法のようなカットインにも、実は“ちゃんとした理屈”があります。
それを理解することで、プレーの見え方や、プレー中の意識がまったく違った角度から見えてきます。
そしてきっと、それがプレーの引き出しを増やすきっかけになるはずです。
ステップ①:おとりの動き(DFを外側へ誘い出す)
サイドでボールを持ったら、
まずは細かいタッチで、相手DFに向かって進みつつ、少しだけ外側(タッチライン際)へじわじわと運んでいく。
するとDFはこう思います。
「こいつ、縦に来るな」
「タッチライン際に追い込んでやろう」
この“縦への警戒”を引き出すことこそが、最初のワナ。ここで相手の意識を一方向に固定するのです。
ステップ②:魔法の瞬間(DFの奥側の足が地面に着いた、その時!)
DFが縦突破に備えて一歩踏み出すと、あなたから見て“遠い方の足”(奥側の足)が地面に着きます。
この瞬間が合図です。
ステップ③:実行!(重心の逆を突き、一気にカットイン!)
奥側の足が地面に着くと、そこに体重が乗り、DFの体は縦方向に対応する準備に入っています。
その一瞬(0.1秒)を逃さず、内側=中央へと一気に切れ込む!
重心を縦に動かしているDFにとって、その逆(内側)に反応するのは、体の構造上ほぼ不可能。
DFの体は一瞬“止まり”、あなたの動きに対応できなくなるのです。
このカラクリに気づいた瞬間、「これは長男と一緒に試してみたい…!」と、ワクワクが止まりませんでした。
ロッベン選手の、あの「分かっていても止められない」カットインの秘密は
相手の重心をコントロールし、 その“頂点”を突くタイミングの妙にあるのだと!

親子で特訓!「DFの足元ガン見」1対1対決で必殺技を磨く!
理論が分かれば、あとは実践あるのみ!
そこから、世にもマニアックな「1対1対決」が繰り広げられることになりました(笑)。
【ボクサカ流・重心ハック体得練習法】
- 攻撃側(長男)とDF役(わたし)で、1対1の状況を作ります。
- 攻撃側(長男)の目的は、ただ一つ! まずは細かいタッチで私を縦に誘い出し、ひたすら私の「長男にとって遠い方の足(奥側の足)」が地面に着く瞬間に、そのタイミングでカットインを成功させること。
- DF役のパパママは、初めはあえて少し大げさに縦を警戒する動きを見せてあげたりすると、お子さんが「今だ!」というタイミングを掴みやすくなるかと思います。
※我が家の場合は、対峙する際、サイドステップ気味に、ジリジリと後ろに下がる動きで対応すると、子供がタイミングを掴みやすかったです。
この練習は、チームの練習がない日や、長男が「パパ!サッカーしたいからサッカーしようぜ!」と言ってきた時なんかに、一緒に行っていました。
長男はもともとカットインが得意だったので、タイミングの習得も比較的スムーズ。
一方、私はというと…かなり苦戦しました(笑)
というのも、子どものステップって細かくて動きが分かりにくいんですよね。
それに加えて、長男のディフェンスが思った以上に“ガチ”でして…そりゃもう容赦なし!
まあ、私のことは置いといて(笑)
この練習を通じて強く感じたのは、
一度ハマると、本当に抜ける!

一度でもこのテクニックが“バチッ”と決まると、もう大人の私でも全くついていけない。
文字通り「体が言うことを聞かない」感覚なんです。
この「絶対に抜ける!」という成功体験は、長男にとって何よりの自信になっていきました。
成功のポイントはこの3つ!
- 完璧なタイミング
相手DFの足が地面に着く瞬間を見極める“観察眼”がすべて! - 爆発的な初速
タイミングを掴んだら、最初の1〜2歩で一気に置き去りに! - 正確なボールタッチ
次のプレー(シュートやパス)につなげる位置に、ピタッとボールを置ける技術がカギ!
慣れてきたら、「スペースを見ながら、間接視野で判断してみよう」なんて、ちょっと無茶ぶり気味な応用練習にも挑戦しました。
でも基本は、遊び感覚で。
失敗したり、動きがぎこちなかったりするのも、また楽しいんですよね(笑)

「軸足リード」で選択肢を増やす
続いて、「軸足リード」でも行います。緩急をより得るための手段として有効。
時間(タメ)を作れるので、上がってきた味方へのアシストなど、プレーの選択肢をより増やすことが出来ます。
正対するため、DFはよりサイドステップ感が強くなり、「”奥側の足”が地面に着く瞬間」という判断が、「こっちの方が分かりやすかった」という選手もいるかもしれません。
この「軸足リード」の構えを自然にできるようになるだけで、相手DFに「こいつ、何かしてきそうだぞ…」という無言のプレッシャーを与えることができる。
特にサイドの選手は、覚えておいて損は無いと思います。
長男に起きた“驚くべき進化”~スペースとDF、二つの景色が見えた日~
時は経ち…
中学生になった長男に、驚くべき進化が訪れました。
元々、彼は低学年の頃に習得した「スペースを見ながらドリブルする」習慣を持っていましたが、
(スペースを見るきっかけになった練習の記事はこちら♪)
この「重心ハック」の練習を通じて、
今度は相手DFの”一点”の動き、つまり「重心移動の起点」に集中するという、新しい視点を手に入れたのです。

ある日の試合で、彼は、いつものようにサイドから仕掛けながら、
目の前のDFに対して、その体の向きや重心の乗り方を冷静に見極めていたんです。
相手の重心を見極めつつ、フェイントの反応次第で、どっちにも抜ける!
という雰囲気を感じ取りました。
そこで、試合後、長男に質問してみたのです

お疲れ♪
今日の試合見たけど、相手の重心見ながら、どっちでも抜けるように見えたよ?
小学生の頃、一緒に色々実験してたじゃん?
今は、相手のどこ見てその判断してるの?

あー…
目の前の相手はあんま見てない。
でも「太ももの筋肉の動き」は何となく意識して判断してる。その瞬間に逆を取ると、上手くいくことが多いんだよね。
でも、何となくだよ?
その言葉を聞いた瞬間、思わず言葉を失いました…

「相手の太ももの筋肉を”関節視野”で見る」までに発展させた長男の進化。
長男は、いつの間にやら
「スペースを意識する」というマクロな視点に、
「相手の体の微細な動きに集中する」というミクロな視点を、
無意識のうちに融合させていたのです!
いやはや、父ちゃん、完全に置いてかれました(笑)。
「感覚」でやっていた得意技が、「理論」という裏付けを得て、
さらに高度な「感覚」へと昇華した瞬間でした。
まとめ
さて、今回は我が家の長男が、「感覚」だけのカットインから、
相手の重心をハックする「理論」に基づいた必殺技へと進化していった、
ちょっぴりマニアックな物語をお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
お子さんが持っている「得意技」。
それは、磨けばもっともっと光る、最高の原石です。
そして、その原石を磨き上げるための最高の砥石(といし)が、
「なぜ、このプレーは上手くいくんだろう?」という、ほんの少しの探求心なのかもしれません。
「感覚」でやっていた素晴らしいプレーに、「理論」という名の羅針盤が加わった時、その得意技は、誰も止められない、お子さんだけの「必”殺”技」へと進化を遂げるかもしれませんよ?
難しく考えすぎることはなく、親子で一緒に
「なんでだろう?」
「こうしたらどうなるかな?」
なんて、楽しみながら、
「とりあえずやってみようか♪」
と、サッカーの奥深い世界を探求して、それを子供と共有していくこと。
その時間が、お子さんの技術だけでなく、サッカーを愛する心を、もっともっと大きく育ててくれるはずです。

次回へ続く!